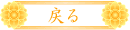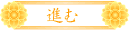役牌 其の5
前回に引き続き、役牌1枚持ちに関して解説していく。
役牌を必要としない手牌














ドラ
東一局北家。
一見してピンフ手で 
 は必要ない、上記のような手牌
は必要ない、上記のような手牌
字牌を扱う上で、一番頻繁に出くわすのがこのパターンである。
では、この役牌をいつ切ればいいのだろうか?
実はこれには明確な答えは存在しない。
まずはこの事を予め明記しておく。
本項では、代表的と思われる2つの切り方を例に取り、その長短所を考察していく。
始めに切る
どうせ必要ないならば、真っ先に切るという方法。
思惑としては、他家に重ねられる前に処理し、後々仕掛けられる危険を無くす事にある。
長所としては、手牌を目一杯広げられる事。
後は思惑通りにいけば、他家の仕掛けの目を始めに摘むことができる。
短所としては、もし鳴かれた場合、役牌という最大の急所を真っ先に献上する結果となる事。
特に北家の場合、親にダブ東を鳴かれると必然的に絞らざるを得ないため、手牌構成に著しい制限が加えられる。
手牌が整ってから切る
取り合えず端牌(上記なら  )から切り出し、手牌がそこそこ整ってから切る方法。
)から切り出し、手牌がそこそこ整ってから切る方法。
思惑としては、他家に鳴かせる前に、手牌を整理してしまう事にある。
長所としては、他家に役牌という急所を仕掛けさせない事。
もし他家が役牌を持っていた場合、危険となる数牌をある程度整理してから勝負できる。
短所としては、手牌構成が手狭になる事。
また、あまり長々と持っていると、他家が重ねてから切り出すという結果になりかねない。