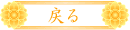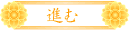南場は場局方針
南場は
- 着順優先
です。
順位を死守、または1つでも上げるための方針、即ち「場局方針」優先となります。
配牌が「風:速攻」タイプでも、ラス目であれば高打点に仕上げる必要があります。
配牌が「火:棒攻」タイプでも、トップ目であれば鳴いて速攻で和了するのが望ましいです。
元々高い手を低く速くすることは比較的簡単ですが、その逆は困難です。
しかし、得点状況がそれを求めるならば、その方針を取らざるを得ません。
この事から、南場で無理な手作りを迫られないためにも、東場で「得点的優位」な状況を築く重要性が浮かび上がってきます。
だからこそ、東場の「場局方針」は「得点優先」なのです。
東場で得点的優位に立てば、南場も「配牌方針」だけで通すことが可能になります。
麻雀は、本来配牌に沿った手作りをすることが一番なのです。
「場局方針」は、あくまでも順位差を考慮せねばならない時に必要なものと考えましょう。
親番による調整
「場局方針」「配牌方針」の判断は、親番の回りによって多少異なります。
南四局で親番が回ってくるのであれば、配牌方針優先を南二局位まで伸ばしてもいいでしょう。
親番は、得点的不利を覆す絶好のポジションです。
そこに至るまでは「配牌方針」優先で被害を最小限に食い止めるのと同時に、僅かでも得点差を詰め、親番で一気に挽回するのも正しい作戦となります。
但し、いくら親番が残っているからといって、安和了するばかりが得策とは言えません。
自分が敵の親番を早く流したいと思うように、敵も、特にトップ目の敵はこちらの親をさっさと流しにくるでしょう。
親番という立場に頼りすぎず、その前から得点の補完を考えることも必要なのです。
また、親番は遅ければ遅いほど有利と言えます。
起家を引いた場合は、勝負所が早く来るという意識を持って闘牌に望むようにしましょう。